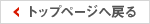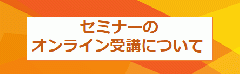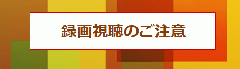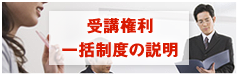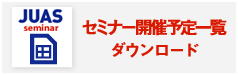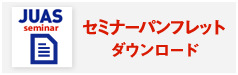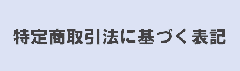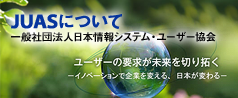わかりやすいマニュアル作成~業務マニュアル・情報共有化文書編 (4119264)
意味が分かる、必要事項への到達が早い、漏れがない わかりやすいマニュアル作成~業務マニュアル・情報共有化文書編 業務マニュアル作成の原点に返り、業務をどう把握するか、それをどう記述するかについて、基礎から学んでいきます。作成の目的・目標の設定、作成計画のつくり方、業務フローの書き方、業務の構成の仕方、改定の仕組みづくりなどを含めて、高度な要求にも対応できるようにいたします。
日時 |
2019年9月12日(木) 10:00-17:00 |
|
|---|---|---|
カテゴリー |
業務遂行スキルヒューマンスキル |
|
講師 |
丸山有彦 氏 |
|
参加費 |
JUAS会員/ITC:33,000円 一般:42,000円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】 |
|
会場 |
||
対象 |
業務の文書化やノウハウの継承の文書化を担当されている方初級 |
|
開催形式 |
講義・個人演習 |
|
定員 |
30名 |
|
取得ポイント |
※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント) |
|
ITCA認定時間 |
6 | |
|
||
主な内容
<<参加者の声>>
・マニュアル作成は要点を押さえて使いやすいものであればいいと聞き、作成に前向きになれた(金融業)
・講師の方の独特のものの見方、考え方が非常に興味深かった(情報システム業)
・業務マニュアルと経営が密接な関係にあるのが驚きましたが、業務マニュアルの意義や価値を再認識できました(金融業)
業務マニュアルのあり方が変化してきています。近年、業務の変化が大きく、従来型の業務手順や、作業を記述した業務マニュアルでは、現実の業務に対応できなくなっています。新たな発想で業務を記述する必要があります。
業務を適切に文章化できたなら業務が見えてきます。業務改革を行う場合にも、業務を把握することが基礎になります。こうした広い用途に対応できる新しい概念の業務マニュアルが必要となっているのです。
業務マニュアルの概念が再定義されたため、作成方法はまだ確立していません。多くの組織で戸惑っているのはこの点です。では業務マニュアルをどう作っていったらよいのでしょうか。
本講座では業務マニュアル作成の原点に返り、業務をどう把握するか、それをどう記述するかについて、基礎から学んでいきます。作成の目的・目標の設定、作成計画のつくり方、業務フローの書き方、業務の構成の仕方、改定の仕組みづくりなどを含めて、高度な要求にも対応できるようにいたします。
ブログで情報発信をしております。 http://mycontentslabo.com/
ご興味ある方は、こちらもご覧ください。
■内容
1 業務マニュアル総論・マニュアル作成は要点を押さえて使いやすいものであればいいと聞き、作成に前向きになれた(金融業)
・講師の方の独特のものの見方、考え方が非常に興味深かった(情報システム業)
・業務マニュアルと経営が密接な関係にあるのが驚きましたが、業務マニュアルの意義や価値を再認識できました(金融業)
業務マニュアルのあり方が変化してきています。近年、業務の変化が大きく、従来型の業務手順や、作業を記述した業務マニュアルでは、現実の業務に対応できなくなっています。新たな発想で業務を記述する必要があります。
業務を適切に文章化できたなら業務が見えてきます。業務改革を行う場合にも、業務を把握することが基礎になります。こうした広い用途に対応できる新しい概念の業務マニュアルが必要となっているのです。
業務マニュアルの概念が再定義されたため、作成方法はまだ確立していません。多くの組織で戸惑っているのはこの点です。では業務マニュアルをどう作っていったらよいのでしょうか。
本講座では業務マニュアル作成の原点に返り、業務をどう把握するか、それをどう記述するかについて、基礎から学んでいきます。作成の目的・目標の設定、作成計画のつくり方、業務フローの書き方、業務の構成の仕方、改定の仕組みづくりなどを含めて、高度な要求にも対応できるようにいたします。
ブログで情報発信をしております。 http://mycontentslabo.com/
ご興味ある方は、こちらもご覧ください。
■内容
・業務マニュアルとは
・業務マニュアルを文書にする理由
・マニュアルの再定義
2 業務の把握の仕方
・目的/目標/手段
・業務の設計と再設計
・構築→運用→改善
3 マニュアル作成計画
・何を目指すべきか:作成範囲
・業務マニュアルの最近の傾向
・マニュアル作成計画の立て方
4 業務フローのつくり方
・業務フローはどうあるべきか
・業務フローの作成演習
5 情報の収集と組織化
・KJ法、ブレインストーミングなどの問題点
・情報の収集法と組織化
・ノウハウ
6 マニュアルの構成法
・文書のユニット構造
・業務の仕組みを作る考え方
7 マニュアル作成のための記述法
・文書作成の構造
・記述のための訓練法
8 マニュアルの改訂
・使いにくいマニュアルを再生させた方法
・マニュアルの評価と改定の仕組み