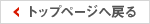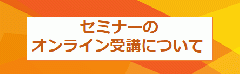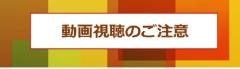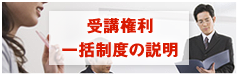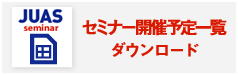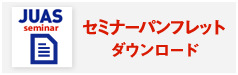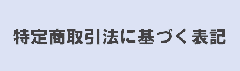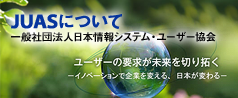ITグループ会社のための下請法の実務とリスク管理【オンラインライブ】 (4125187)
本セミナーは下請法対象取引の一つである「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」(情報システムの開発・運用・保守の分野)に焦点を絞り、下請法の内容とリスク管理について解説します。(下請法全般につきましても,基本的な解説をいたします。)
日時 |
2025年6月12日(木) 9:00-16:00ライブ配信 |
|
|---|---|---|
JUAS研修分類 |
共通業務(契約・法務・コンプライアンス)、プロジェクトマネジメント(プロジェクトマネジメント) |
|
カテゴリー |
共通業務(契約管理、BCP、コンプライアンス、人的資産管理、人材育成、資産管理)・セキュリティ・システム監査専門スキル |
|
講師 |
近藤學 氏 |
|
参加費 |
JUAS会員/ITC:35,200円 一般:45,100円(1名様あたり 消費税込み、テキスト込み)【受講権利枚数1枚】 |
|
会場 |
オンライン配信(指定会場はありません) |
|
対象 |
ITグループ会社、情報システム部門の契約担当者、プロマネ、調達担当者中級 |
|
開催形式 |
講義 |
|
定員 |
25名 |
|
取得ポイント |
※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。(2時間1ポイント) |
|
ITCA認定時間 |
6 | |
主な内容
■受講形態ライブ配信(Zoomミーティング)【セミナーのオンライン受講について 】
■テキスト
開催7日前を目途にマイページ掲載
■開催日までの課題事項
特になし
ITグループ会社は親会社との情報システム開発委託契約に基づき協力会社にシステム開発を委託します。
システム開発では仕様変更が頻繁に発生します。これは下請法上、どのように評価されるのでしょうか。
現在、コンプライアンス(法令遵守)経営が重視されています。この法令違反は風評リスクを招く恐れが多々あります。
大手企業の資材調達・購買部門には監督官庁による調査等が実施されています。
現在は物の製造(製造委託)が中心ですが、このところ,「業務システム」・「製品組み込みの各種制御システム」等、ソフトウェアの重要性は益々高まっており、今後は不適切な取引・やりとりは企業リスクに繋がる可能性があります。
本セミナーは下請法対象取引の一つである「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」(情報システムの開発・運用・保守の分野)に焦点を絞り、下請法の内容とリスク管理について解説します。
(下請法全般につきましても,基本的な解説をいたします。)
◆主な研修内容:
1.コンプライアンスの重要性とリスク管理
・コンプライアンスとは
・コンプライアンス違反とリスク
・コンプライアンス活動の枠組み
・情報成果物の作成委託で下請法が問題になった事例
2.下請法(下請代金遅延防止法)の概要とポイント
・下請法の目的
・下請法の位置づけ
・下請法適用取引の判断基準と要件
・情報成果物の作成委託とは(他の3類型についても解説)
・下請法の適用関係と親会社・子会社の関係
・4つの義務内容と判断基準
・11の禁止事項と遵守のポイント
3.4つの義務内容と実務上の留意点
・注文書の作成・交付義務と留意点
-基本契約と個別契約(注文書と請書を含む)でやり取りする場合の留意点
-電子発注の留意点
・書類の作成・保存義務の留意点
-保存が必要な書類例
-見積書の扱い,提案書の扱い
・支払期日を定める義務と留意点
-大規模システム開発の場合
-工事進行基準による場合
・遅延利息支払義務と留意点
-検収、受け入れテストと支払いの関係
-60日の起算点と利率
4.11の禁止事項の要点と,実務にあたって生ずる問題と対応策
・11の禁止事項とは(要点整理)
・仕様変更、納期変更問と代金変更
・先行作業とプロジェクトの中止
・AI開発のように自社では開発出来ない分野の開発委託
・受注ができないための契約解除
・システム開発プロジェクトが中止になり先行作業が不要になった
・担当者が納品書・請求書の提出を忘れ支払遅延
・無理な納期の指定
・「予算がない」「次回にカバーする」と説明して委託金額を値下げ
・発注者のコンピュータを使用した場合の納品時期とは
・発注者の施設、機器の利用に伴う賃料問題(労働局の指導)
・大規模システムにおける検収期間
・仕様不適合、欠陥を理由とした支払拒絶、受領拒絶
・大規模な開発における部分納品と委託金額支払時期の関係
・知的財産権の委託元への移転問題
・発注単価の一方的値下げ
・品質が悪い場合、減額できるか
・仮単価、仮委託金額、仮納品の問題…ほか
・運用業務など毎月支払いをする場合の留意点
5.官庁による下請法遵守状況調査と下請法事件処理の実際
(1)官庁による下請法遵守状況調査
(2)下請法事件処理フローチャート
(3)下請法運用強化の流れ
(4)下請法運用基準改正とその対応